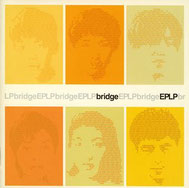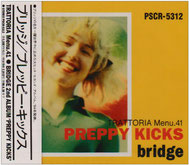自分たちのことで精一杯で、余裕がなかったんですよ

──バンド解散の理由は何だったんですか?
池水 「一言だと方向性の違いってことになるのかな」
カジ 「当時ヴォーカルの眞美ちゃんから続けるのが難しいという話があったんですよ」
池水 「新聞でもその話は載ったんですけどね。でも実はアルバム『SPRING HILL FAIR』を出した後の段階で方向性について迷いがある話は出ていたんですよ。そのときはもう少しやってみようよと一度落ち着いたんです」
カジ 「確かシングル『PAPER BIKINI YA-YA』を出したあとぐらいだったよね」
池水 「あと、1stアルバムをリリースするまでにブリッジは一気に盛り上がってしまったから、その反動もあったんじゃないかなって思うんですよ。ブリッジは本当に恵まれていて、初ライヴをやったあとすぐにあちこちから声がかかったんです。ヒット・パレード(the hit parade)やモノクローム・セットとのライヴの話が飛び込んできたり。まだライヴ1回しかやっていないのに・・・」
カジ 「あとは盛り上がっていく過程でブリッジの音楽性もどんどん変わっていったから、それもあったんだろうね」
清水 「だから今回の再結成ライヴで眞美ちゃんが喜んでくれたのが本当に嬉しかったんだよね。20年近く経ってひとまわりもふたまわりもしたんだろうけど、やっぱりバンドっていいもんだなって思えたみたいだし…当時、バンドのフロントマン・ヴォーカリストとして少し荷が重くなってしまったんじゃないかな。僕らがもっと大人でフォローしてあげられていれば違ったのかもしれないけど、まだ若かったし」
池水 「自分たちのことで精いっぱいだったもんね」
カジ 「当時はみんな音楽だけじゃなく、普通に他の仕事やバイトをしながら活動してたしね」
池水 「女子はみんな会社員だったよね。OLやりながら夜や週末にレコーディングしていたからね」
カジ 「そんな感じだったので、ブリッジはライヴツアーをすることは出来なかったですね。二足のわらじでとても忙しかったし、今もそうだと思うけどメジャーでやっていくというのは、ある種の競争環境の中に放り込まれることなので、みんな躍起になっていたからね。荷が重くなってしまったというのはよく分かります」
──ただ、ブリッジ解散後も皆さんは各々ソロで音楽活動を続けられて今に至るわけですから、音楽への情熱を失ったわけではなかったんですね。
カジ 「それは全く逆ですね。僕は大きな野心も情熱も持っていたし、プロとして活動したかった。たぶん清水君や大橋君もそうだったと思う」
池水 「カジ君は特にそうだよね。間髪入れずにカジヒデキ名義で活動していたし」
カジ 「みんなそうだよね。清水君もすぐにソロや新しいユニットをはじめたし、池水さんもソロで始めたしね」
清水 「音楽をここまでやれるとは思わなかったな。まあ綱渡りだけどさ(笑)」
音楽のスタイルやサウンドにこだわっていた

──先日のライヴを観てブリッジはライヴバンドだったのだろうなと感じました。(スタジオ)アルバムはネオアコ特有のキラキラした感じが前面に出ているんですけど、ライヴは音がゴリっとしており想像以上にグルーヴィーで、ロックバンド顔負けの重厚感あふれるギターサウンドも。
清水 「それは昔からよく言われるね」
カジ 「決してライヴの本数が多かったわけではなかったんだけど、ライヴは大好きだったんですよ。トラットリアからデビューする前までは自主企画のライヴもよくやってましたね。デビュー決まってからはレコーディングでスタジオに入る機会がスゴく増えたので、おのずと本数が減ってしまいました」
──話は変わるのですがブリッジはもともと英語詞の歌が多かったわけですけど、ミニアルバム『PAPER BIKINI YA-YA』以降は日本語詞中心へ変更されています。
カジ 「当時はまだ英語詞の歌が市民権を得ていなくて、日本ではなかなか売れなかったんですよ。今もそうだね(笑)。フリッパーズ・ギターもデビューアルバムは英語詞だけどシングルの『恋とマシンガン』や2枚目の『カメラ・トーク』から日本語詞になったじゃない。90年代後半のハイスタの大ブレイク辺りから英語詞でも売れる人が出てきたけど、それは稀で、当時のメジャーの環境ではなかなか難しかったんです。当時複数のレコード会社から日本語でやるんだったらいいけど、英語にこだわるんだったら難しいと言われて断られましたね」
池水 「今だったらもう少し自由なんだろうけどね。当時メジャーで英語詞をやることは本当に難しかったんです。ポリスターはそういう意味では懐の深い会社だったんですよ」
カジ 「1枚英語詞でリリースしたあと、レコード会社から日本語詞にもトライしてみたらと提案されたこともあったし、僕らももうワンステップあがっていくためにチャレンジしてみようと思ったんです」
──実はこれまでに取材したほぼ100%のバンドが同じことを話していたんですよ。皆さんインディーズ時代には英語詞で作って歌っていても、メジャーデビューする際には日本語詞に変更されていて。それはレーベルからの要請があってのことで、レーベル側もビジネスとしてやっていくためにはそうしないと売れないという現実もわかっているからそうせざるを得ない。作家性とのバランスをどう取るのかは難しい問題です。
池水 「でもフリッパーズ・ギターがいいお手本を作ったというのは大きいかな。フリッパーズ以降それで日本語詞も増えていった気がするし」
カジ 「本来ネオアコのような音楽をやるんだったら、語感やスタイル含めて英語詞のほうがフィットするとは思うんですよ。でもフリッパーズはネオアコの良さを生かしながら日本語でもうまくやれることを証明したんですよね。だから90年代当時のレコード会社もそのような意識を持っていたんじゃないかな。でも実際にやると音楽性やスタイル含めて歌詞の世界観を融合させるのはとても難しい作業でしたね(笑)」
──歌詞を読むとブリッジは風景描写や何気ない日常の出来事について多く歌われていますよね。恋愛についても間接的な言い回しを好まれているように感じました。政治的なメッセージだったり、例えばストレートに“アイラヴユー”と気持ちを表明するようなラブソングを歌ったりはしていませんよね。
カジ 「ブリッジは歌詞よりも音楽のスタイルやサウンドにこだわっていたからね。もちろん歌詞も重要なんだけど、先にスタイル、ネオアコ特有の感覚を大事にしていたというか」
池水 「歌を作る時も曲が先にあったんですよね。歌詞を先に考えてあとから曲をつけるといったことはしていなかったんです。例えば〈Windy Afternoon〉は私が作った曲なんですけど、これも曲を作ったあとに“Windy Afternoonというイメージで歌詞を作って”と眞美ちゃんにお願いしたことをすごく覚えていて(笑)。何かを強く訴えたいという感じはなかったけど、何かの気持ちを伝えるにしてもフィルターを通したいというのはあったよね。英語詞にしていたのもそういう理由があったと思う」
カジ 「若さもあっただろうし、素直に“アイラヴユー”とは逆に言いたくはないという当時の空気感もあったんですよ」
清水 「当時〈Kiss My Thought Good-By〉だったかな、ブライアンに詞を書いてもらったときに違和感があって。ずっと眞美ちゃんが歌っていたのを聴いていたから、語感の違いになじめなかったことがあったんだよね。やっぱりさ、サウンド重視でやっていたんだなって振り返ってみて思うよね。もちろん歌詞を全く重んじてなかったわけではなくてね」
池水 「言葉よりも音符を重視していたといったらいいかな」
清水 「だからかな…今回再結成して久々にブリッジをやることになったけど、今やっても違和感のない歌が多いんだよね。当時のその場の感情ありきだったら、今は恥ずかしくてできない歌が多かっただろうね」
──作品のクレジットを見ると、ソングライターが多いのもブリッジの特徴だと感じました。全員が曲を書くんですか?
池水 「ドラムのヒロちゃん以外の5人は書いていましたね」
清水 「そういえばそうだな。ヒロちゃんにも一曲くらい書いてもらえばよかったね」
──ソングライターが5人もいるバンドは珍しいですよね。選曲はどうされていたのでしょうか?
池水 「毎回オーディション状態だったんですよ(笑)」
カジ 「確かに珍しいかもね。普通はメインソングライターがいたりするんだろうけど、みんな書けたからね」
──ソングライターが変わると楽曲の傾向も変わると思うんですけど、ブリッジの場合ソングライターが変わってもブリッジとして聴こえる特有の感覚がとても不思議だったんです。もちろん〈SPLASH〉のように清水さんが曲を書いて歌も歌っているような場合は個性をより色濃く感じますけど。
清水 「多分、ドラムの影響がデカいんじゃないかな。リズムってとても大事でヒロちゃんのドラムはとても個性があるからね」
池水 「あとは眞美ちゃんが歌うとブリッジになるというのはあるよね。最初のころは誰ともなく、とにかく曲ができたら都度それぞれ持ち寄って、レパートリーをどんどん増やしていったんですけど、1stアルバムリリース以降はみんながデモを作ってきて、都度オーディションをしていました」
──アレンジはどうされていたんですか?
池水 「ブリッジってバンマスがいなかったよね(笑)。だから作曲者が責任を持ってアレンジまでやるというのが基本的なやり方だったかな。そしてソロパートはアコーディオンソロなら私が、ギターソロなら清水くんが考えてきました」
カジ 「サウンド面で言うと、『SPRING HILL FAIR』まではプロデューサーの小山田君と清水君の2人が中心になってまとめてくれた感じですね。時間をかけてレコーディングをしたので、なかなか全員がスタジオにいる機会がなかった。『PAPER BIKINI YA-YA』以降は各作曲者が最後まで責任をもってイニシアティブをとってやっていましたね」
清水 「サウンド面で僕が参考にしていたのは60年代の古いミュージシャンの音で。例えばビーチボーイズのコーラスの感じだったりとか。古いジャズの録音も好きだったからジャズの要素をちょっと入れてみたりね」
──ネオアコなんだけど、色んなジャンルの音が混ざっているのも独特だなと感じていたんですよ。
清水 「僕らの世代ってレコードから入って、当時はCDが出たばかりのころで。古いものから新しいものまで分け隔てなく聴いていたからその影響があるのかもね」
ブリッジはやっぱり自分たちの原点ですよね

──今回ブリッジを待っていたファンがものすごく多いことに気付きました。SNSや周りの友達の反応もすごいですし、今までブリッジの話をしなかった友達からも実は好きだったんだよねという話が多くて。4月のライヴチケットも即日完売でしたよね。
カジ 「僕も想像以上の反響に、正直驚いています(笑)。ツイッターの反応もすごかったですね。最初は渋谷クアトロとかも考えたのですが、イベンターもレコード会社のサポートもない完全自主企画なので、リスクは背負えないし、実際アストロホールでもチケットが売り切れるか不安だったんです」
池水 「新譜のリリースがあるといったトピックがあったわけでなかったしね」
──最後に、ブリッジは皆さんにとってどんな存在ですか?
清水 「僕にとっては原点かな…今はエンジニアの仕事、ミックスやマスタリングなどの仕事もしているんだけど、ブリッジでやり始めたんですよね。三つ子の魂百までじゃないんだけど、その元になった存在のバンドがブリッジ」
池水 「音楽人生の中でなくてはならない大事なものかな。ブリッジをやっていた当時は、このバンドをやるために音楽をやってきたんだなって思ってました。その後はソロでThree Berry Icecreamをやってきて、もちろんそれも大事ですが、また今回ブリッジをやるにあたってそれも役立ったというか…」
カジ 「やっぱり自分の原点ですよね。今はソロでやっているけどブリッジがなかったら音楽をやっていたかもわからないしね。それだけいいメンバーに出会えて、いい環境に恵まれて作品を作れたというご縁に感謝しています」
──ありがとうございました。
ブリッジ作品