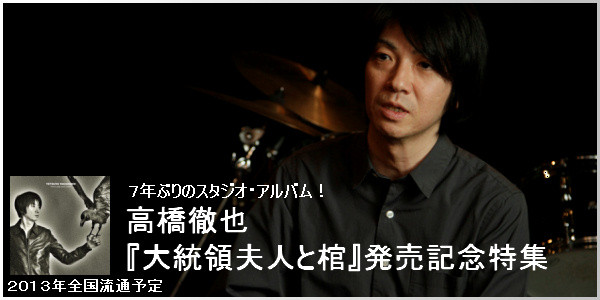自然現象を歌うのは今回チャレンジでしたね。

──ライヴで鍛え上げてきた曲が多いと思うのですが、アルバムのために用意した曲もあるのですか?
高橋 「アルバムのためにっていうと「大統領夫人と棺」と「ハリケーン・ビューティ」と「ブラックバード」の3曲ですね。この3曲に関しては歌詞のワード自体、普段自分が使っていないのが結構あって。自然現象を歌うこと・・・台風の歌とかそういうのを今まであんまりやったことがなくて自分としてはトライという面もあり面白いなと思いました。それが本にある地図というか、いわゆるロードムービー的な感じにリンクできるなと」
──その他にも影響を受けたものってありますか?
高橋 「海にまつわる物語というのはずっとあるかもしれないですね。ライヴDVDもそうですが常に海があって。サマセット・モームというイギリスの小説家がいて、彼の作品の中に南洋シリーズがあるんですけど、そのイメージはすごく強いですね。あと、暖かいところで暮らしている人ってちょっと異常な感性があるような気がしているんです。中南米の作家の本を読んでいるとすごく変な寓話があって“寝れなくて羊の数を数えていたら数が足りなくなってしまった男”とか、そういうのが普通に近所にいるみたいな(笑)。“シーツを干していてそのまま洗濯物に包まれていなくなってしまった少女”とか、そういうのが普通にニュース欄に載ったりしているんですよね。ガルシア=マルケスの小説とかね。それが自分としては面白くて影響を受けていますね」
──他には1969年に公開された映画『真夜中のカウボーイ』のラストシーンとか高橋さんらしいと思いました。海に辿りついて、死んでアロハ着ている感じとか(笑)。
高橋 「そうですね、でも全然海行かないんですけどね(笑)」
──確かご出身は埼玉でしたよね?キリンジとかにも感じるのですが、海のない都道府県の郊外感というか、一筋縄ではいかない感じとか、湘南の人間にはない感性をお持ちだなあと思います。ちなみに旅にはよく行かれるんですか?
高橋 「いや、ほとんどしないですね(笑)。でも「Key West」、「サンディエゴ・ビーチ」、「Praha」っていう曲もそうですけど、かえって行ったことのない奴の間違った認識による面白さもあると思うんですよね。自分としてはその感じっていうのはしっくりきますしね」
──佐野元春さんの「バルセロナの夜」という歌があるのですが、全然バルセロナじゃないらしいんです(笑)。それでもやっぱり佐野元春ファンはバルセロナに行くらしいんですよ。実際に行って“全然違う!”と言って帰ってくるという(笑)。
高橋 「佐野さん好きなんですよ。ビートもそうだし、アメリカ文学のような感じがするところとか。偶然でも似たような感覚があるならばそれは嬉しいですね」

ちゃんと本題を話すというか、強い音楽を作りたいという想いがあるんですよ。今回の作品はそれを実現できたと思います。

──本の話が出ましたけど、確かヘミングウェイもお好きなんですよね?
高橋 「そうですね。今は「サマセット・モーム」と「ガルシア=マルケス」と「ヘミングウェイ」の3人ですね。巨人って感じで。悲しい男の小説って結構読んできた気がするんだけど、あまりにも身も蓋もなくて(笑)。背景が南洋というか海とか明るい空間なんだけど、そこで暮らす孤独な人達というコントラストが好きで、今回のアルバムの「Key West」なんてもろにそうだし、「不在の海」というインストルメンタルの曲があるんですけど、それもヘミングウェイの解説に出てくるんですね。結構それは・・・怒られるくらい影響を受けていますね(笑)。あとライヴDVDにある「サンディエゴ・ビーチ」という歌のように、地名や人名を曲にしたいという願望もすごくありますね。内容は全然そこに結びつかないようなダークなストーリーなんだけど(笑)」
──海外文学の世界ですよね。ちなみに翻訳された日本語で読む外国文学なり思想って独特の味わいがあると思いませんか?
高橋 「そうですね。多分ものすごいこじつけ方とかがあって(笑)、それがかえってロックというかパワーを感じます」
──高橋さんの物語性はやっぱり音楽で表現されているのが面白いと思います。
高橋 「僕もたまにちょっとした小説まがいのようなものを書いてみたりするんですよ。でもやっぱりあんなにできないし音楽の中のト書きみたいな。歌詞ってやっぱりそういう気持ちなんですね。音楽があってそれを少し補足しているというか・・・言い切らないというのが自分は好きなので。でも言い切らないとヒットしないんですよね(笑)。でもそれは一生を賭してやろうと覚悟は決めました」
──大きな物語の一部を歌っているイメージもありますが。
高橋 「物語性みたいなものはだんだん意識するようになりました。世の中はいわゆる恋愛ソングみたいなものが主流じゃないですか?それだとやっぱり面白くないんですよね。なんか表現したいものがあるんですよ」
──新譜の歌詞がすごくポジティヴに聞こえました。1曲目の「ブラックバード」は前作からの連続性を凄く感じる歌なんですが“何があったんだ、高橋徹也?”といった空気を感じたんですよ(笑)。8年という年月があるんだけれど、その間にすごい転換があった気がします。
高橋 「(以前と比べて)すごく素直に書くようになりましたね。あとは大きな災害があってそれに対する反応が、人気あるないに問わず踏み絵みたいにあって・・・どういう態度をとるんだ・・・それはすごい隅から隅まで用意周到にそのシステムができていて・・・やっぱり“それについてどう思うか?”というのがあって。自分はずっと“変わらない”スタンスでやっているんですけどね。今も昔もずっと言われていることとかを大事に思ってやってきているし、何かを変える必要はないし。でもそれに付属している絆とか、そういうワードを持ち出してくるムードなどには“このやろう”というのがあって(笑)。その現象そのものではなくて、それにまつわるムードみたいなものには“ピシと背筋伸ばして行こうぜ!”というのはあったと思いますね。あとやっぱり強い音楽を作りたいという想いがすごくありますね。元々自分はアフター渋谷系みたいなところが出てきて、あいまいに濁した感じがカッコイイみたいなところで来ていたと思うんですけど、もっとちゃんと本題を話すというか・・・この『大統領夫人と棺』は、自分にとってそういうものとフィクションをうまくバランスとれないか? というところでやりましたね」